江戸開城後、西郷隆盛は会津の為に『戊辰戦争』継続!ホント?
すべてに寛容なイメージの大人物西郷隆盛が、なぜ『戊辰戦争』では会津を救わなかったのかの理由を明確にします。
『尊皇(そんのう)』と言いながら、なぜ孝明天皇に尽くしていた『会津藩』が”朝敵”となったかを考えます。
奥羽鎮撫総督府の下参謀世良修蔵(せら しゅうぞう)はなぜ殺されたのかを明らかにします。
目次
官軍は、なぜ会津藩と戦闘を行うのが既定方針だったの?
『戊辰戦争』と言えば、”会津の悲劇”と言うようなイメージが出来上がっています。
NHK大河ドラマ『八重の桜』でも、会津藩の幕末の動向が悲劇的に会津藩サイドからの視点で描かれていました。
日本人の判官びいき的な面もあり、敗軍”会津藩”への同情心もあり、歴史と云う観点よりはどちらかと言えば”ドラマ”的な視点で見てしまうことはあるかと思います。
つまり、『忠臣蔵』と同じように、史実よりは”義”の世界を描く方が話になるということでしょうか。
『忠臣蔵』で言えば、”主君浅野内匠頭(あさの たくみのかみ)に対する忠義”で、『会津藩』の松平容保(まつだいら かたもり)公で言えば、”徳川幕府に対する忠義”と言う事ですね。
そういう流し方でこの出来事を理解してしまうと、どうも実態が分からなくなりそうです。
”幕末・維新”の話と言うのは、勝者と敗者がいます。後々にもずっと『薩長政治』・『薩長人脈』など用語がたくさんあるように、出来上がった新政府が『勝者』の立場での歴史づくりをしたために、真相がよく分からなくなっています。
『歴史づくり』には、論外の荒唐無稽な話をでっちあげるものから、都合の良い出来事だけを都合のよい理由付けをして取り上げて行き、その他の出来事は無視をしたり、はなはだしきは都合の悪い歴史資料を破棄する・なかったことにすることまであります。
そうするとこれが後世になると”史実”とは違うものが、教科書に載る『歴史』として認知されて行くことになる訳です。
そこで、、、会津の話です。。。
言葉は悪いですが、”官軍の会津イジメ”と言う観点で『戊辰戦争・会津戦争』を見てしまうと、”恨みつらみ”のオンパレード・ごちゃごちゃで話の収拾が取れなくなりそうです。
ここで、慶応3年(1867年)末の”薩長”の『武力討幕行動』が始まった段階で、薩長サイドに想定された抵抗政治勢力を私の後知恵で整理をしてみますと、
- 徳川慶喜と大政奉還(公儀政体論)グループ
- 幕府(江戸の幕閣)
- 会津藩(と桑名藩)
嘉永6年(1853年)7月8日の『ペリー来航』に始まった幕末の動乱は、安政7年(1860年)3月3日の『桜田門外の変』で幕府大老井伊直弼が水戸浪士に暗殺されて以来、政局の中心が完全に江戸から京都へ移ってしまい、諸藩は薩長を中心とする西国の雄藩以外は京都の政局を”様子見”する形になりました。
『安政の大獄』で水戸藩が弾圧されたあと、長州藩が文久2年(1862年)から動き始め、京都でテロ活動を開始して政局の混乱を引き起こします。
そして実は本当に暗躍し始めたのは、長州テロ勢力・尊攘運動に便乗して、久々に日本の歴史の表舞台に出て来て朝廷政治を動かす多数の公家たちでした。
徳川幕府(大老井伊直弼)は、御三家水戸の徳川斉昭(とくがわ なりあき)が折角家康以来武家が抑え込んでいた”公家勢力”を利用したため(これがどうも「パンドラの箱」を開けたことになったようです)、水戸藩に手を掛けると同時に、ストレートに水戸とともに暗躍した公家たちも弾圧します(安政の大獄)。
しかし、一度永い眠りから覚めた公家勢力は幕府の弾圧くらいでは収まらずに、武家勢力(薩摩、長州、会津、幕府、徳川慶喜等)を使い分けて、訳の分からない騒乱の幕末が演出されて行きます。
ここで、一番後世の私たちがよく分からないのが、幕末で有名な『尊皇攘夷』派の”尊皇・勤皇”の”天皇”の扱いです。
尊皇攘夷思想・運動の元祖となった水戸学派の藤田東湖と長州の吉田松陰が敬う”天皇”は、当時の今上天皇である『孝明天皇』だったはずなのですが、今上天皇”孝明天皇”は、徹底してこの攘夷志士たちとそれを輩出する藩を嫌います。
そして、孝明天皇は幕府寄りの考え方を示し、最後にふらふらとなった徳川慶喜をもかばい続けます。
この時点で孝明天皇は、”朝廷を敬うはず勤皇の志士たちと倒幕運動の藩”とは、完全に敵対しているのです。
この孝明天皇の意向・命令に従順に付き従って行動していたのが、会津藩主松平容保(まつだいら かたもり)率いる会津藩の京都駐屯軍です。
つまり、徹底した勤皇思想で今上天皇である孝明帝の信頼厚い会津の行動に、”尊皇”を掲げて政局に関与している長州藩が、”恨み骨髄の敵のように反発する”と言う極めておかしな構図になっている訳です。
事実、元治元年(1864年)7月19日に長州藩過激派が引き起こした『禁門の変』の時には、会津藩と薩摩藩(この時までは会津と蜜月関係?)が協力して長州の暴発の鎮圧に当っているのです。
この時薩摩は会津と同じ勤皇派だったのです。そしてどう見ても長州は”孝明帝”を支える勤皇派ではないのです。
明治以降の日本の歴史教科書はこの矛盾に全く答えようとしていません。
そして事態は、慶応2年(1866年)12月の”孝明帝崩御”によって、一気に展開して行きます。
孝明帝を軍事力で支えていた会津藩は、忽ち政局からずり落ちて、新帝?(明治帝)を支える長州派(叛乱派)公卿たちと下級公卿岩倉具視、そして長州藩と今度はこちらへ鞍替えした薩摩藩が政治の表舞台に躍り出ます。
この頃長州の桂小五郎(木戸孝允)が、『玉(天皇)』は確保?したと言っています。
新帝を確保?することによって、ほぼ政権を取った(まだ幕府があるにもかかわらず)に等しい薩長が、最後まで薩長に反攻する勢力として強烈な勤皇藩である『会津』を『朝敵』として攻撃するのです。
会津藩を徹底して潰す戦争を仕掛けるのが『既定方針』であったと言うその理由は、どうやら会津藩が、新政府(薩長)の担いだ『玉(明治帝)』ではない、先帝の”孝明帝”を担いでいた(信頼の厚かった)ことのように見えます。
これは日本の歴史によくある過去の朝廷の帝位継承争いと同じだ、と言ってしまえばそうなのかもしれませんが、一応、明治帝は孝明帝の息子とされていますので親子なのです。
会津があくまでも薩長の政局運営に逆らう動きをし続けた理由は、個人的な恨みつらみを別にすれば、やはり『天皇』であったように思えます。
要するに、薩長新政府がどうしても会津を滅亡させねばならなかった大きな理由も、そこ(全く不敬な話ながら、おそらく新天皇の正統性)にあったのではないでしょうか。
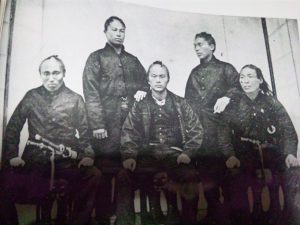
(画像引用:慶応4年戊辰戦争出征前写真)
会津藩は、幕府の命令に従って京都の治安維持に勤めただけなのに、なぜ薩長に恨まれるのか?
最初はまさにその通りで、幕命とは言え自身が病弱でさらに藩内の猛烈な反対もあり、会津藩主松平容保(まつだいら かたもり)は『京都守護職』就任を固辞し続けたものの、幕府重鎮越前藩主松平春嶽(まつだいら しゅんがく)の『会津の藩祖保科正之(ほしな まさゆき)公なれば、お受けするであろう』の一言に、会津藩主松平容保は将軍家茂(とくがわ いえもち)を助けるために『京都守護職』就任を渋々受けます。
そもそも”京都守護”は、京都所司代の仕事ですが、この時期文久年間は長州発と考えられる”尊攘志士”たちの激しいテロが横行して京都の治安は極度に悪化し、所司代の武力では到底抑えることなど出来ない状況となっていました。
同時に、幕府の組織した”対テロ対策用”の浪士隊(京都では”新撰組”)も、会津藩の指揮下に入ります。それで、京都の治安維持と云うものは、いうなれば御所(天皇・朝廷)のガードマンも兼ねることとなります。
こうした中、松平容保は、今上天皇である孝明帝の信頼を得て行くこととなります。
幕府大老井伊直弼の暗殺(1860年3月3日)以降、急速に時代の政局が幕府(江戸)から朝廷(京都)へ移って行き、孝明帝の政治的発言力が高まって行きます。
時間の経過とともに、孝明帝の近くにいて信頼が厚く、かつ江戸の将軍家茂の信頼も厚いことから、会津公松平容保の幕府内での影響力は強まって行きます。
つまり、最初は幕命で京都の警護にあたる任務だけのはずが、どんどん京都(朝廷)の政治力が高まるにつれて、容保は江戸の幕閣をも凌駕する発言力を持ち始めます。
薩長のような反幕府勢力には、”新撰組”の活躍とともに、(薩長のみならず、京都市民にまで)敵役として会津藩が認知されて行く事となりました。
長州藩が仕掛けた”禁門の変”で京都市内の大半が焼失したのも、会津の責任と思われて京都市民に悪印象を与えたようです(なぜか京都市民は長州藩に同情的なのです)。
『大政奉還』後の慶応3年(1867年)12月9日に、薩摩西郷隆盛と大久保利通、公卿岩倉具視らによって京都御所で決行された『王政復古のクーデター』の事前の”諸藩動向分析”においても、西郷隆盛の結論は『新しい政治状況に反対し抵抗を続けるのは、会津藩と桑名藩だけだ。』というものでした。
元将軍の徳川慶喜より会津の方が厄介だと西郷は考えていたわけです。
このように会津藩は、薩長から単純な”恨み”とか言うレベルではなくて、幕藩体制護持に固執して新体制に馴染もうとしない問題児(異端児)で、”粛清対象”として薩長維新の政治家たちに認知されて行きます。
西郷は、江戸の治安維持を担当し、『江戸薩摩藩邸焼討ち』を行なった荘内藩にはなぜ寛大だったの?
会津藩が京都の治安を守る役割だったのに対して、荘内藩は江戸の治安を守る役目を幕府から与えられていました。
配下には、有名な京都の”新撰組(しんせんぐみ)”の分派である浪士隊の”新徴組(しんちょうぐみ)”がいました。
当初の与えられた状況としては、会津藩とほぼ同じものでした。
荘内藩にとってラッキーだったのは、政局が江戸から京都へ移って行き、台風の目である天皇・朝廷が現代のように江戸城にいなかったことです。
つまり、荘内藩は会津藩のように幕末の政局に影響を及ぼす立場に置かれることはありませんでした。
しかも、加えてラッキーだったのは、実は薩摩藩と荘内藩は友好関係にあり、討幕軍の大将格である西郷隆盛は荘内藩の理解者でもありました。
これは、下記関連記事で紹介しましたように、荘内酒田の豪商本間家の分家出身の洋学者本間郡兵衛(ほんま ぐんべえ)が、偶然、薩摩近代化の功労者でもあったことです。
西郷隆盛は、”戊辰戦争”の折、前線指揮官の黒田清隆(くろだ きよたか)に『酒田湊は本間北曜先生の生まれ故郷だから、政府軍が勝ちに乗じて醜行を働いてはなりませんぞ』と指示を出しているほど気を使っていました。
荘内藩は、本間家の財力のお陰で、戊辰の戦いで近代装備と強兵をもって鳴り響き、奥羽列藩の中心である会津藩が降伏しても、まだ官軍との継戦体制をとっていたほどでしたが、官軍の責任者が西郷と知ると説得に応じて帰順しました。
当初は西郷が担当していましたので、荘内藩が考えていた通り、官軍サイドはそのまま荘内藩の本領安堵する寛大な措置を取ろうとしてましたが、長州の大村益次郎が軍事力に優れた荘内藩を危険視して、徹底処分を強硬に主張し会津の地への”移封”が官軍より命じられます。
しかし、結局、偶然?発生した大村益次郎の暗殺事件と本間家の政治工作が功を奏したのか、70万両の”献金(罰金・賠償金)”が命じられるに留まり、同じ”処分”でも会津藩とは大きな違いを見せました。
会津藩に戦いを避ける手立てはあったのか?
先ず、会津藩が戦を避ける第一、最大のチャンスは、京都守護職を藩主松平容保が何を言われようが、固辞し続けることだったと言えそうです。
勿論そうなれば、”会津の悲劇”は、生まれなかったことになりますが、百戦錬磨で老獪な越前藩主松平春嶽に半分脅されて、これを藩主松平容保が引き受けてしまったことから悲劇の会津幕末史が始まってしまいました。
春嶽に言われたように、容保は”会津の藩祖保科正之の徳川家を守ると言う精神”に極めて従順でしたが、当初は熱狂的な勤皇家ではなかったように見えます。
しかし、『京都守護職』に就任して、孝明天皇との関係が深まるとともに、徳川家の守護ではなくて、孝明天皇に取り込まれて勤皇家へ変身して行きます。
そして孝明帝の影響を強く受けて、尊攘志士もびっくりの勤皇攘夷派になって行き、そのため容保と京都家臣団は、会津の国元家臣団・江戸家臣団と遊離して、まるで”孝明帝のしもべ”と化して行きます。
そこから、悲劇の本番が始まったと言えそうです。
国許・江戸表ともに心配する中、容保と公用人をトップとする会津藩京都駐屯部隊は、長州藩との対立を深めて行き、幕府からも諸藩からも孤立して行きます。
他藩や幕閣からみれば、幕府の京都守護職に過ぎない会津藩が、朝廷(孝明帝)の力を背景に政局を動かそうとしているように受け取られ、幕府からも薩長からも信じられないことに『政敵』と見られて行きます。
もう助かる方法は、何らかの理由をつけて、京都守護職を辞職して国許に引き上げるしかなかったと言えます。
所謂”諸侯会議”に出る雄藩の藩主たち(土佐の山内容堂、越前の松平春嶽、薩摩の島津久光、伊予宇和島の伊達宗城など)は、何度もさっさと仕事を放り出して国許へ平気で引き揚げて行きます。またそれも政治駆け引きのひとつだった訳です。
一方、会津藩主松平容保は政治家やはりではなかったと言う事で、そんな政治力もないただまじめなだけの藩主を戴いた会津藩士たちの運命はどんどん暗転して行きます。
何度か訪れる帰国のチャンスをことごとく、容保の”生真面目さ”と”義に厚い律儀さ”が潰して行きます。つまり、軍務に耐えられないような脆弱な体にも拘わらず、放り出して帰国するような無責任なマネが出来ない性格なのです。
私見ですが、あの時あの立場での最良の選択肢は、、、
会津の京都駐屯の初期段階で薩摩側から持ち掛けられた関係強化があります。
それに拠って、『文久の政変』・『禁門の変』を共同して戦い、薩摩の政治的立場を長州から奪い返すのに手を貸してやったわけですから、おそらく、これを梃子に薩摩との関係を更に維持強化しておけば、会津が助かる道は開けていたような気がします。
容保が気が付かなければ、補佐役である公用人がそれをしなければいかなかったのですが、あろう事か薩会盟約の主役の公用人秋月悌次郎(あきづき ていじろう)を北海道へ左遷させると言う大失態を犯していたのです。
結果的に会津はすべての選択肢を自ら潰して行きました。主君松平容保は将器としては凡人だったと言わざるを得ませんが、だからこそ、それを支える会津京都家臣団、特に公用人の責任は重いと言わねばなりません。
西郷にとって、会津を含む東北への戦いは必要だったの?
後年の私などが思うよりはるかに西郷隆盛と言う人物は好戦的であったようです。そもそも戦国期の武将と云うものはそんなものなのかもしれません。
幕末期の難局を運にも恵まれ、極めてうまく乗り切って来た西郷にとって、どこと手を結んでどこと手を切るかの選択は先天性も手伝った彼の”勝負勘”と云うものなのでしょう。
前章で見てきたように、会津にとって最悪だったのは味方のはずの薩摩と自ら手を切ってしまったことでした。
西郷側も結局徳川家支配の幕府から離れようとしない会津と組んで行くよりは、九州の南端に位置する薩摩からみて本州の入口にある長州と手を組む方が戦略的には叶っていると考え、会津を切って長州と手を結ぶ道を選択します。
丁度その時、前述したように薩摩との重要な繋ぎ役をしていた公用人秋月悌次郎(あきづき ていじろう)を、会津藩が自ら藩内抗争で左遷させてしまったのです。
これで、西郷は無理難題を仕掛けなくとも、穏便に会津と薩摩の公式の関係を終了させることが出来、長州との関係構築に政策転換をしました。
その後会津は薩摩があろうことか長州と組んだことを知って臍を噛む(ほぞをかむ)こととなります。慌てて秋月悌次郎を復帰させてみましたが、もはやあとの祭りで、西郷の考え方は前述のとおりで、秋月は相手にされませんでした。
こうした前段はあるのですが、朝敵とされて京都での活動を大幅に制限される長州に替わって、反幕府勢力として主に活動する薩摩藩、対旧体制護持勢力を代表する『一会桑(一橋慶喜、会津藩、桑名藩)』との対立はエスカレートして行き、会津藩は旧幕勢力を代表する武闘派となって行きます。
その後も、会津藩は、薩摩の大久保・西郷の政治行動にことごとく盾突いて行くことになります。
そして『幕末維新』のクライマックスも近づいた、慶応3年(1867年)10月14日の将軍徳川慶喜の『大政奉還』後は、朝廷中心の政治体制構築を目指す薩摩藩グループと、幕府への大政委任復活を目指す会津藩グループにハッキリ分かれて鋭く対立をしていく構図となります。
さらに、将軍慶喜の移行した新政体への居残りを打破するために薩摩グループによって仕掛けられた12月9日の『王政復古のクーデター』により、朝廷中心の新政府樹立が確定し、それからの政局の焦点は、新政府内でどちらの勢力が政権の座に就くかと言う話に大きく変化して行きます。
西郷にとって、最初の相手は幕府(徳川家)のはずだったのですが、この辺りから許しがたい『政敵・ライバル』として”会津藩”が認識されていきます。
こうして『会津』は、完全に殲滅せねばならない政治勢力として、西郷をはじめとする薩長勢力によって位置付けられます。
”江戸城開城”後に、上野の彰義隊を壊滅させて、幕府の本拠地”江戸”での戦いを終息させた西郷は、最後まで薩長新政府の対抗勢力として侮れない軍事力を持つ”会津藩”の討伐に取り掛かります。
西郷が考えた『戊辰戦争』における所謂”東北戦争”の主眼は、”会津藩の殲滅”なのです。
つまり、江戸で旧幕府(徳川家)を降伏させただけでは、新政府は安心して新国家体制建設に着手できないため、西郷としては”会津”を屈服させるためにどうしても『東北戦争』は必要だったと言えそうです。
官軍(奥羽鎮撫総督府)下参謀世良修蔵(せら しゅうぞう)はなぜ殺されたの?
世良修蔵は、長州高杉晋作(たかすぎ しんさく)が創設した奇兵隊出身で、奇兵隊総監をしていた赤禰武人(あかね たけと)に引き立てられ、慶応元年(1865年)の高杉挙兵時、第二奇兵隊軍監に昇進しました。
しかしその後、赤禰が高杉晋作と対立して失脚すると、世良も巻き添えを食い謹慎していましたが、鳥羽伏見の戦い以後の長州藩の戦力補充で京都へ呼ばれ、前職が再評価されて幹部扱いとなり、この東北戦争で鎮撫総督府の下参謀に取り立てられました。
つまり、本人は何とか手柄を立てて奇兵隊での失点を取り返したい一心で功を焦っている人物でした。
総督に任命されたのは公卿の九条道孝(くじょう みちたか)でしたが、実際の奥羽鎮撫総督府の実権はこの世良修蔵と同じ下参謀の薩摩大山格之助(おおやま かくのすけ)のふたりが握っていました。
官軍(新政府)から仙台藩に対して会津の追討命令が出されており、乗り込んだ大山と世良は、会津討伐へ出かけようとしない仙台藩主伊達慶邦(だて よしくに)に向かって、傲岸不遜の態度で会津への侵攻を督促し攻めたてました。
世良が狂気のように叫ぶたびに、居並ぶ仙台藩士は屈辱に体を震わせていたといいます。
世良修蔵の出身が武士ではない漁師上がりで足軽以下の低い身分人間であることも知れており、『朝廷』と言う虎の威を借りて、仙台藩をなめ切った態度で周囲に毒をまき散らしていました。
仙台藩は、やむなく会津国境へ出陣したものの本気戦う気がなく戦況は膠着状態で、世良と大山の苛立ちは最高点に達していました。
実は、官軍から仙台藩への出陣命令が出てすぐに、”『禁門の変』を犯した長州藩への寛大な処分と較べた今回の会津藩への厳しい処分に疑問を呈する建白書”をもって京都の総督府へ代表を派遣しました。
京都で対応に出た当時参謀の黒田清隆は、”会津は長州藩の場合とは事情が大きく違う。皇威を奥州に及ぼすには、会賊は飽くまで屠らざるを得ない”と説明しています。
官軍(西郷隆盛)は最初から会津を助ける気持ちは全くなく、むしろ『生贄(いけにえ)』にするつもりだったようです。
やむなく仙台藩は会津藩への征討戦を進めながらも、裏で会津・荘内救援運動を取り進めていました。
つまり、東北の『奥羽列藩同盟』で会津藩・荘内藩救援のため、官軍との戦争状態に入る準備をしていた訳です。
そんな中、”碌に会津も攻めれない腰抜け侍である仙台藩以下の東北人が官軍参謀の自分を襲ってくるはずがない”と侮っている世良修蔵でした。
しかし、4月19日に世良の福島における定宿”金沢屋”で、盛大な宴会を福島藩に開いてもらい、機嫌よくそのまま飯盛り女と同衾していた世良を、20日に未明に仙台藩士を中心とした誅殺隊が襲いました。
実は、数日前から世良を襲う準備をして世良を追っていたものの、決心がなかなかつかず踏み切れずにいましたが、この日に世良が、大山に対して飛脚便で送ろうとした書状に”奥羽皆敵と見て”とあるのを発見して、激高し誅殺決行に踏み切ります。
襲い掛かった藩士に対して世良は、護身用に所持していたピストルで応戦しようとしますが、不発に終わり裸で2階から飛び降りたものの頭部を石垣にぶつけて負傷し、裸体のままその場で取り押さえられます。
宿の裏から連れ出され、阿武隈川の河原でそのまま、斬首されました。
丁度、白石城に集まっていた奥羽列藩の重臣たちは、世良の誅殺の知らせを聞いて涙をながしたり、歓声をあげて喜んだと言います。
またこの日、慶応4年(1868年)4月20日に会津軍が白河城の奪取に成功して、奥羽鎮撫総督府と薩長軍に根拠地を失わせましたが、この時から『奥羽列藩同盟』の官軍との実に5ヶ月に及ぶ”東北戦争”が始まったのです。
世良は政府軍参謀の地位をひけらかし横暴であり、性急傲岸に奥羽諸藩に出兵を強要して回ったのですが、官軍の方針に忠実であったとも言えます。
結果的に誅殺された世良は、官軍に対する『奥羽列藩』諸国の戦争被害の恨みを一身に受ける役割を演じることなり、まるで官軍の『生贄(いけにえ)』にされたようにも感じます。
ひょっとしたら、これも西郷隆盛の”挑発行為”のひとつだったのでしょうか。
まとめ
冒頭にも述べましたように、『戊辰戦争』は”会津の悲劇”を以って語られることが多く、そうしたストーリーを聞かされることばかりですが、会津を襲った悲劇の悲惨さに覆い隠されている歴史の真相を知ることも必要ではないでしょうか。
今回は『東北戦争』の仕掛け人であった西郷隆盛の行動の理由を見てみる事としました。
西郷の行っていた『戊辰戦争の討幕戦』に関しては、慶応4年(1868年)4月11日の”江戸城開城”にて終結したはずで、その後の残存抵抗勢力の掃討戦として『上野彰義隊との戦い(上野戦争)』も終えました。
しかし、幕府がすでに降伏したにもかかわらず、戦いは終わらずに東北へと続いて行きます。
実はすでに慶応4年(1868年)1月の段階から東北への討伐戦は計画に組まれていたのです。
それは、、、
慶応4年(1868年)1月17日に、京都に逗留していた仙台藩家老但木土佐(ただき とさ)は、京都御所内の政府政庁に呼びつけられ、『会津藩追討令』の文書を渡され、会津討伐を命じられました。
慶応4年正月の『鳥羽・伏見戦争』が終わってすぐに、薩長軍はすでに『会津討伐』を決めていたということです。
政府部内には、穏健派(寛典処分派)と強硬派(武力討伐処分派)に分かれていましたが、当初2月9日に総督に沢為量(さわ ためかず)、参謀に長州品川弥二郎(しながわ やじろう)、薩摩黒田清隆(くろだ きよたか)となっていましたが、2月26日に総督が沢から九条道孝(くじょう みちたか)、2月30日に黒田から大山格之助(おおやま かくのすけ)、3月1日に品川から世良修蔵(せら しゅうぞう)にと交代になり、3月2日にこの『奥羽鎮撫使』は京都を出発しました。
2月17日に”容保死罪”の会津藩の厳罰処分案が出されましたが、どうもそれから、メンバーが穏健派から強硬派へ変った様子です。
いずれにせよ、黒田清隆が参謀に内定していた時に、仙台藩の密使に答えた折、『会津の討伐』はすでに決まっていることを告げています。
このように、黒田がこう云ったと言う事は、西郷がそう考えていいることになり、会津を最初から討伐することで、政府内は一致していたと思われます。
ただ、幕命に従って京都の警護(京都守護職)についただけのはずの会津藩が、なぜこのように最後の最後まで薩長から目の敵にされていたのか?ですが、、、
長州には、長州が主催する”尊攘テロ活動”をことごとく邪魔され、挙句、文久3年(1863年)の『文久の政変』で、長州が朝敵にされたことを恨まれました。
薩摩には、幕府・朝廷の中で動く政局の中で、京都二条城と御所のただの用心棒だったはずの会津藩が孝明天皇の庇護を受け、ひとつの政治勢力として、権力奪取を夢見る薩摩の前に大きく立ちふさがるようになり、政敵として始末する対象となって行ったことでした。
薩長各々に敵視される理由を作ってしまった会津は、京都に出てきたが故の悲劇に見舞われたことがよく分かるわけです。
開国を迎える幕末の時代の奔流に、まともに巻き込まれて、国政の権力闘争に揉みくちゃにされたことが、会津藩の悲劇の本質だと考えられます。
始めから政権奪取の気があってで京都進出して来たのならまだしも、徐々にその立場へ追いやられ、最後は徳川家と同じ扱いで悪者扱いされたと言う、『会津藩と藩主松平容保』は通説通りに非常に気の毒な人達であったとも言えます。
しかし、会津の人たちの頑張りが幕末の政治勢力を成長させ、新政府(薩長閥)に対する大きな批判勢力の存在を意識させたことも、その後の日本の発展に寄与したことも間違いないことであろうと思います。
こう見て来ると、、、
会津は、理由もなく一方的にいじめられたり、生贄とされたわけではなく、彼らが行ったことが歴史上で最も人的犠牲を強いることの多い政治権力を握ろうと意図した行動であると周囲から受け取られたことが原因と言えそうです。
ここでは、『戊辰戦争』当時、西郷隆盛の”会津”に関しての政治姿勢は、『討伐方針』だったと言うことがわかりました。
参考文献
〇家近良樹 『孝明天皇と「一会桑」』(2002年 文春新書)
〇星亮一 『奥羽越列藩同盟』(2009年 中公新書)
〇星亮一 『偽りの明治維新』(2008年 だいわ文庫)
〇中村彰彦 『鬼官兵衛烈風録』(2015年 日経文芸文庫)
〇中村彰彦 『落花は枝に還えらずとも』(2008年 中公文庫)
〇佐高信 『西郷隆盛伝説』(2010年 角川文庫)
〇安藤優一郎 『幕末維新の消された歴史』(2014年 日経文芸文庫)
〇佐々木克 『戊辰戦争』(2011年 中公新書)
〇綱淵謙錠 『戊辰落日』(1978年 文藝春秋)